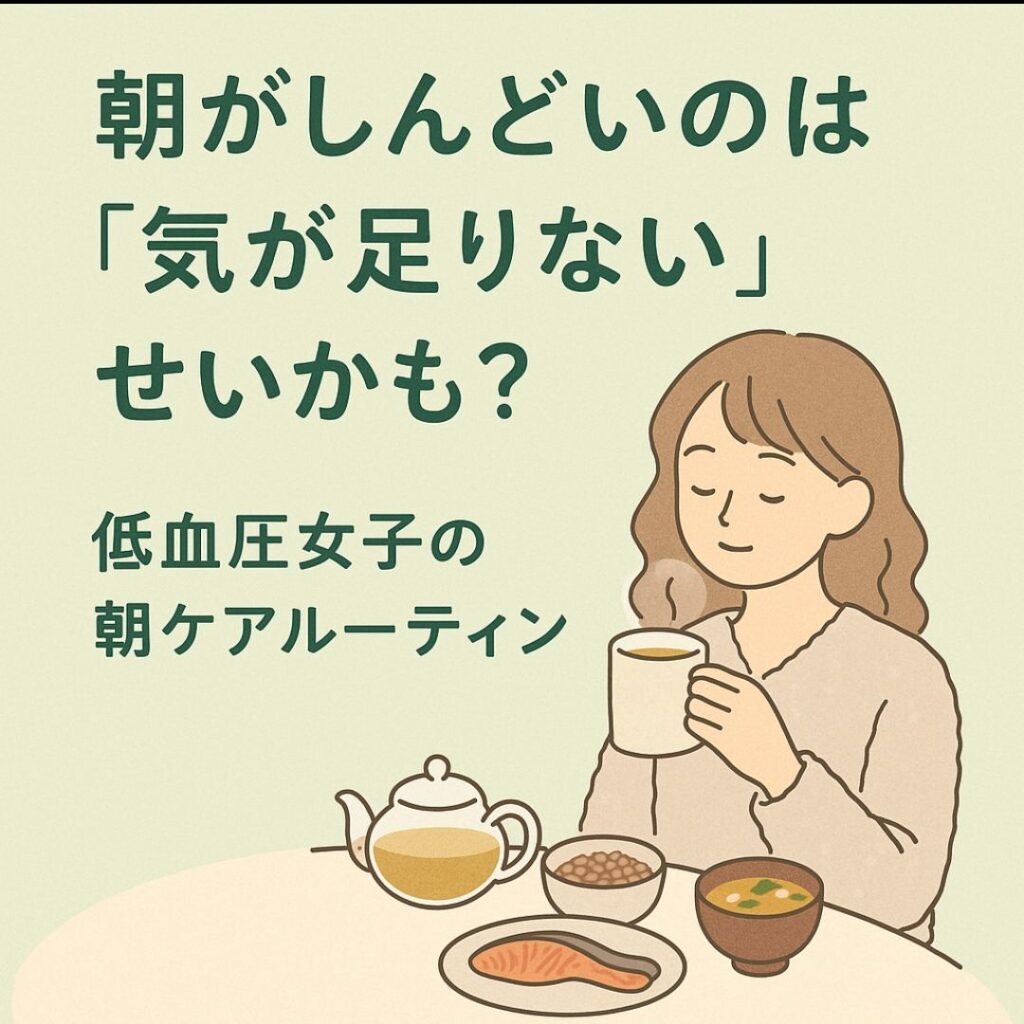― それぞれの“こころの居場所”について ―
人との距離感は、性格や経験によって大きく違います。
たとえば、
「誰かと一緒じゃないと落ち着かない」人がいます。
逆に、
「ひとりでいる時間こそが救い」だと感じる人もいます。
どちらが正しい、どちらが強い、なんて話ではありません。
それは、心の地図が違うだけなのです。
—
💠 誰かがいなくちゃいられない人のこころ
このタイプの人は、
・LINEが返ってこないと不安になる
・週末に予定がないと落ち着かない
・「ひとりの時間」をうまく過ごせない
そんな傾向があります。
でもそれは、甘えではなく、
「こころの安心基地」を外に求めているから。
幼い頃に、
孤独を怖いと感じた経験があるのかもしれません。
あるいは、誰かといることでしか
「自分の存在」を感じられなかったのかもしれません。
その人にとって、
“誰かのそば”は、心が生きるための酸素のようなもの。
—
💠 一人が楽な人のこころ
一方で、
「人と一緒にいると疲れる」
「予定のない時間が一番ホッとする」
「返信を無理に返したくない」
そんな感覚を持つ人もいます。
このタイプの人は、
人との距離感を敏感に感じ取り、
自分のエネルギーを消耗しやすい傾向があります。
誰かと一緒にいる時間、
「嫌われないように」「期待に応えよう」と
知らず知らずのうちに自分を演じてしまうことも。
一人の時間が長いのではなく、
一人の時間でやっと“自分”に戻れるのです。
—
🌿 どちらでもいい。ただ、あなたが“安心できる場所”が大切
「一人でいられる自分ってすごい」でもないし、
「誰かといたい自分はダメ」でもない。
大事なのは、
“あなたが安心できる距離感”を知ること。
他人に合わせすぎて疲れてしまったとき、
一度こう問いかけてみてください。
> 「私は今、誰かといたい? それとも、一人になりたい?」
答えは日によって違ってもいい。
人との距離感は、“今の心”の温度計みたいなものです。
—
💬 最後に:どちらのあなたにも、優しさを。
「寂しがりな自分」も、
「一人でいたいと思う自分」も、
どちらもあなたの一部です。
どちらかに偏りすぎてしんどくなったら、
心の声を聞いてあげてください。
あなたの“安心できる場所”は、
他人の価値観じゃなく、あなた自身が決めていいのです。
カテゴリー: 自分で出来る心体ケア
-
誰かがいなくちゃいられない人と、一人が楽な人
-
花火大会に誘われたけれど──人との距離感に気づいた日
夕方、友人から「花火大会、一緒に行かない?」と誘われた。
その一言に、心が少し沈んだ。
「ああ…行きたくないかも。」
そう思った自分に、ちょっと驚いた。
—
花火大会なんて、きっと綺麗だし、楽しいはずなのに。
それでも、心がズンと重くなる。
「行かなきゃ悪いかな」「でも疲れそう」
頭の中で何度も言い訳を探している自分がいた。
—
でもふと、気づいたことがある。
もしこれが家族とのお出かけだったら、平気だったかもしれない。
—
家族となら、
黙っていても気まずくない。
無理にテンションを合わせなくていい。
疲れたら「帰ろう」と言える。
それって、わたしにとってすごく大きな安心。
—
わたしがしんどくなるのは、
「人といること」ではなくて、
**“気を使いすぎてしまう状況”**だったんだと、ようやく気づいた。
—
誰かと過ごす時間を楽しめる日もある。
でも、どうしても重たく感じてしまう日もある。
そんなときは、自分の感覚を信じてあげようと思う。
—
行かない選択をしたことは、
“わたしの心にやさしくした”という、ちいさな一歩だった。
—
🌿あとがき:
人と距離をとることは、わがままじゃない。
それは、自分の呼吸を守ること。
わたしは今日も、静かな部屋でひとり、遠くの花火の音を聞きながら、
自分の心とつながっている。 -
ビタミンCの正しい摂り方|ストレスや風邪に効く「腸耐性量」とは?
—
あなたのビタミンC、本当に足りてる?
「果物を食べてるからビタミンCは大丈夫」と思っていませんか?
実は現代人は、ストレスや環境要因、病気、疲労などにより、
想像以上にビタミンCを消耗しています。そして、そのときに必要な量は、人それぞれ。
必要量を見極めるヒントが、「腸耐性量(ちょうたいせいりょう)」という考え方です。—
ビタミンCの「腸耐性量」とは?
ビタミンCを大量に摂ったときに、
お腹を壊さずに吸収できる最大量のことを「腸耐性量」といいます。ストレスが強い時、風邪を引いた時、手術後などは、
この腸耐性量が通常の数倍〜十数倍まで跳ね上がることがわかっています。—
症状別・1日のビタミンC最大摂取量の目安(腸耐性量)
状態・症状 1日あたりのC量(g) 回数(分けて)
健康時 4〜15g 4〜6回
軽い風邪 30〜60g 6〜10回
重い風邪 60〜100g以上 8〜15回
インフルエンザ 100〜150g 8〜20回
アレルギー(花粉・食品) 15〜50g 4〜8回
外傷・手術 25〜150g 6〜20回
精神的ストレス 15〜20g 4〜6回
慢性炎症・関節炎 15〜100g 4〜15回出典:Helen Saul Case『Orthomolecular Nutrition for Everyone』
—
どう摂ればいいの?
ビタミンCは一度に大量摂取すると下痢を起こす可能性があります。
そのため、「分けて」飲むのがポイント。摂取のコツ:
1回あたり3〜5gを目安に
食後か、空腹時を避けて摂る
水と一緒にしっかり飲む
パウダータイプなら水やスムージーに混ぜてOK
—こんな時はビタミンCを多めに摂ろう
風邪のひき始め
精神的ストレスが強いとき
睡眠不足が続いたとき
肌荒れや疲労がひどいとき
PMSや生理前後でメンタル不安定なとき
ビタミンCは、抗酸化・抗ストレス・免疫サポートの三本柱で、
あなたの体と心をしっかり守ってくれます。—
⚠注意点・よくある質問
Q:飲みすぎて大丈夫?
A:水溶性なので余分な分は尿で排出されます。
ただし、胃腸が弱い方は下痢や腹痛に注意してください。Q:毎日10g以上は多すぎ?
A:体が必要としていればOK。
ストレス・風邪・炎症などがあると、必要量は数倍になります。Q:腎臓に負担は?
A:結石や腎疾患の既往がある方は、医師に相談の上で使用を。
—
まとめ
✅ ビタミンCの必要量は「状況」によって変化する
✅ 腸耐性量を目安にすると、自分に合った摂取量がわかる
✅ ストレス・風邪・疲労のある人は積極的に摂取を
—
こんな人におすすめの記事です:
疲れが取れにくい方
子どもの風邪が気になるママ
肌荒れ・ストレスが続いている女性
サプリをうまく活用したい健康志向の方
—

-
朝がしんどいのは“気が足りない”せいかも?
朝がしんどいのは“気が足りない”せいかも
低血圧女子の朝ケアルーティン【中医学×分子栄養学】
—
朝がつらい。気合いではどうにもならない…
わたしは毎朝、6時に目覚ましをセットしています。
けれど実際に体を起こすのは、まるで重い岩を動かすよう。
目は覚めているのに、身体が動かない。呼吸も浅く、指先が冷えている。
「甘えてるのかも」「頑張って起きなきゃ」と、何年も自分を責めてきました。でも、あるとき健康診断で「血圧が低すぎますね」と言われて気づいたのです。
わたしの“気合い不足”は、実は【気の不足】だったのかもしれない、と。—
中医学の視点:「気虚」はエネルギーのガス欠状態
中医学では「気=生命エネルギー」と考えられています。
食べ物を消化して、栄養をめぐらせ、気血をつくる。
でも、その“気”が不足すると──起きられない
息切れする
動くとすぐ疲れる
頭がボーッとする
生理前後や低気圧でさらに悪化
そんな「気虚(ききょ)」状態に、わたしはずっといたのかもしれません。
—
わたしの「気を補う」朝ケアルーティン
今では、朝を“戦い”ではなく、“準備”の時間に変えました。
覆1. お臍まわりマッサージ(10分)
仰向けで優しくお腹をほぐすことで、内臓を温めて“エンジン起動”。
2. 肩まわし左右100回ずつ
肩・背中・肩甲骨の血流を促し、上半身にエネルギーをめぐらせる。
3. 朝のお茶
桂枝、麦冬、百合、玫瑰花、赤棗、枸杞 をポットで蒸らして
白湯代わりにゆっくり飲みます。身体の内側からぽかぽかに。4. 朝ごはんは「炭水化物少なめ粥+温菜+発酵食品」
黒豆・赤豆・薏苡仁などの雑穀粥
鮭と玉ねぎの炒めもの
納豆
お味噌汁
ご飯の量は80gくらい。でも、完全に炭水化物を抜かないのが大事。
泥5. モコモコの冬用パジャマで寝る
冷房が体にこたえる夏。「冬用寝巻き+靴下」が冷え予防に◎
6. 出発前に“15分横になる”
仕事前、アラームをかけてベッドで一息。
「起きたら休む」が、今の私の回復戦略です。—
補足:分子栄養学で見た朝のしんどさ
分子栄養学でも、「朝起きられない」原因は栄養不足とされます。
特に必要なのはこの4つ:1. ビタミンB群(エネルギー産生に必須)
2. 鉄(フェリチンが低いと酸素不足)
3. タンパク質(神経伝達物質の材料)
4. マグネシウム(神経の興奮を調整)
→サプリで補うだけでなく、朝のご飯に炭水化物とタンパク質を少し入れることが、朝のエネルギー切れを防ぎます。
—
まとめ:怠けてるんじゃない。“燃料切れ”なんだ
朝、起きられない日があっても大丈夫。
それは「あなたが弱い」からじゃなくて、
身体が「助けて」と言ってるだけ。気を補って、温めて、少しずつ休ませてあげる。
それが、わたしの“気虚ケア”です。—
✏️今日のひとこと
> 「朝のつらさは、わたしのせいじゃなかった。
“気が足りない”わたしに、そっと寄り添ってあげよう。」